まえがき
扉を開ける前のあなたへ
ずっと、”良い子”でいなければ、と頑張ってきた、あなたへ。
「ちゃんとしなきゃ」と、自分を縛りつけてしまう、あなたへ。
でも、本当は、心のどこかで叫んでいませんか。
完璧じゃない私を、誰か、見つけて、と。
これは、一匹の、どうしようもなく不完全な猫が、 あなたの心の檻を、そっと開けてくれる物語。
もう、”良い子”にならなくてもいいんだよ、と、 その温かい寝息で、教えてくれる物語です。
『その猫は、”良い子”ではなかった』

長谷川怜(はせがわ れい)、三十五歳、弁護士。
彼女の世界は、常に、寸分の狂いもないロジックと、コントロールされた秩序で成り立っていた。
彼女の口癖は、「ちゃんとしなきゃ」。
その言葉は、クライアントに、同僚に、そして何よりも、彼女自身に向けられた、厳格な呪文だった。
都心のタワーマンション二十階にある彼女の部屋は、その哲学を完璧に具現化した空間だった。
白とグレーを基調とした、ミニマルなインテリア。
全ての物は、定められた場所に、定められた角度で置かれている。
床に落ちた一本の髪の毛さえ、彼女にとっては、世界の調和を乱す不協和音だった。
感情という、非効率的で予測不能な要素は、この完璧な城では、徹底的に排除されるべきものだった。
そんな怜が、保護猫を引き取ることに決めたのは、ある種の、極めて論理的な判断に基づいていた。
一つ、社会的評価の高い弁護士として、動物愛護という社会貢献活動への参加は、ブランディングに寄与する。
一つ、孤独な独身生活における、ストレス軽減効果が、科学的に証明されている。
一つ、世話を通して、他者への共感能力を養うことは、仕事にも好影響をもたらすはずだ。
彼女は、恋人や友人を選ぶように、いや、それ以上に慎重に、パートナーとなる猫を選んだ。
保護猫カフェのサイトで、何十匹もの猫のプロフィールを、まるで判例を読み込むかのように、徹底的に分析した。
そして、彼女が選んだのは、「リク」という名の、二歳のキジトラのオスだった。
「他の猫とあまり群れず、自立心旺盛。静かな環境を好む」という紹介文が、彼女の完璧な日常に、最もスムーズに溶け込むだろうと判断したのだ。
しかし、そのロジックは、リクが、彼女の完璧な城のドアをくぐった瞬間、音を立てて崩壊した。
リクは、怜が予測したような「自立心旺盛で、静かな猫」では、全くなかった。
彼は、恐怖に支配された、小さな獣だった。
キャリーケースから出た途端、低い唸り声を上げ、怜が完璧に整えたリビングを、パニック状態で駆け回り、そして、陽の光を美しく透過させるはずだった、純白のレースのカーテンに、その鋭い爪を突き立てた。
ビリビリ、という、怜の鼓膜を引き裂くような音。
レースは、無残な姿で、床に垂れ下がった。

リクは、怜が近づけば「シャーッ!」と威嚇し、怜が用意した、オーガニックで、栄養バランスの計算され尽くしたフードには、一切口をつけなかった。
彼が唯一口にするのは、怜が軽蔑していた、安価で、添加物まみれのウェットフードだけ。
そして、怜が大切にしていた、海外の有名デザイナーが手掛けたクッションの上で、粗相をした。
それは、怜の完璧な日常と、彼女が何年もかけて築き上げてきたプライドに対する、全面的な宣戦布告だった。
***
怜の、静かな戦いが始まった。
彼女は、この「問題児」を、論理的に「矯正」しようと試みた。
週末、彼女はブックカフェ《月光蟲》の隅の席で、猫の行動心理学に関する専門書を、何冊も、何冊も読み漁った。
付箋を貼り、マーカーを引き、まるで裁判の準備書面を作成するかのように、リクを「あるべき姿」へと導くための、完璧な行動計画を立案した。
【フェーズ1:環境適応の促進】
計画に基づき、怜は、科学的に猫が安心するとされる、フェロモン拡散機を設置した。
リクが好みそうな、様々な種類の爪とぎや、おもちゃを買い揃えた。
しかし、リクは、その全てを、まるで存在しないかのように、完全に無視した。
彼は、ただ、ソファの下の暗闇から、疑心暗鬼に満ちた緑色の瞳で、怜を監視し続けるだけだった。
【フェーズ2:ポジティブ・リンフォースメントによる信頼関係の構築】
次に、怜は、リクが唯一好むウェットフードを使い、「ご褒美」によるしつけを試みた。
リクが少しでも落ち着いた様子を見せれば、フードを与える。
しかし、リクは、フードを食べ終えると、すぐにまた、唸り声を上げて、闇の中へと消えてしまう。
彼女の存在は、ただの「給仕係」としてしか、認識されていないようだった。
【フェーズ3:問題行動の是正】
爪とぎ以外の場所で爪を研ごうとすれば、大きな音を立てて注意を引く。
粗相をすれば、消臭スプレーで匂いを完全に消し去り、そこに柑橘系の香りを置く。
本に書かれている「正論」を、彼女は、一つ、また一つと、完璧に実行していった。
しかし、リクの行動は、何一つ、改善されなかった。
それどころか、彼の人間に対する不信感は、日増に強まっていくようだった。

そして、ある雨の夜。
怜の忍耐は、限界に達した。
仕事で、理不尽な要求を繰り返すクライアントに、終日、振り回された日だった。
疲れ果てて帰宅すると、リビングの床に、怜が大切にしていた、ベネチアングラスのオブジェが、粉々に砕け散っていた。
リクが、棚から落としたのだ。
その、きらきらと光る、修復不可能なガラスの破片を見た瞬間、怜の中で、何かが、ぷつりと切れた。
彼女は、ソファの下に隠れているリクを、半ば強引に引きずり出した。
怯えて、体を硬直させる小さな体。その、恐怖に満ちた緑色の瞳。
それでも、怜は、その体を強く掴んだ。
その瞬間、リクは、恐怖のあまり、体のすべての力を抜き、ぐったりと、まるで生命のない、ただの毛皮の塊のようになってしまったのだ。
その、抵抗を諦めた、絶対的な無力感の塊を腕に感じた瞬間。
怜の全身の時間が、止まった。
――リビングの、真っ白な絨毯。
そこに、五歳の自分が、オレンジジュースをこぼしてしまった、あの日の午後。
母の、氷のように冷たい手が、自分の腕を強く掴む。
恐怖で体が動かなくなり、母のなすがままに引きずられていく、あの時の、無力な自分。

腕の中のリクの姿と、記憶の中の幼い自分の姿が、完全に、重なった。
私は、今、この子に、母と全く同じことをしている。
私が、あんなにも憎んでいた、「正しさ」という名の暴力を、この、か弱い生き物に、振りかざしている。
腕の中で、リクが、小さな体で、必死に震えている。
その、恐怖に満ちた緑色の瞳。
そこに映っていたのは、かつての、親の期待に応えられず、ただ、怯えていた、幼い自分の姿だった。
ああ、私は、なんて、愚かなことをしていたのだろう。
「…怖かったよね」
怜の喉から、絞り出すような声が漏れた。
腕の力を、そっと緩める。 「ごめんね。本当に、ごめん」
リクは、腕から解放されると、すぐにまた、ソファの下の闇へと逃げ込んだ。
怜は、その闇に向かって、静かに語りかけた。
それは、過去の自分自身に、語りかけるように。
「もう、”良い子”にならなくて、いいんだよ」
彼女は、ゆっくりと立ち上がると、リクのために用意した、檻のように感じていた、大きなケージの扉を、静かに開け放った。
***
その日から、怜の戦いは、終わった。
彼女は、リクを「しつける」ことを、完全にやめた。
本は、全て、クローゼットの奥にしまった。
カーテンは、ズタズタのまま。時折、物は壊されるし、粗相も、完全にはなくならない。
けれど、怜は、もう、それを、正そうとはしなかった。
ただ、壊れれば修理し、汚れれば、黙って掃除した。
彼女は、ただ、静かに、リクと同じ空間にいることを、自分に許した。
リクが安心できる距離を、保ち続けた。
無理に、近づかない。無理に、触らない。
ただ、彼が、ここにいても安全なのだと、感じてくれるまで。
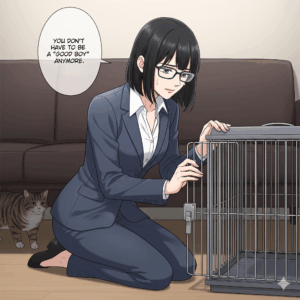
数週間が過ぎた、ある夜だった。 大きな訴訟の準備書面を読み込み、心身ともに疲れ果てた怜は、ソファで、うたた寝をしてしまっていた。
ふと、右腕に、そっと、小さな、しかし、確かな重みを感じた。
そして、温もり。 怜は、夢と現実の狭間で、ゆっくりと、目を開けた。
腕が、動かせない。
そこに、小さな、茶色い毛玉が、香箱座りをしていたからだ。
リクだった。
彼は、ソファの下の闇から、自らの意志で、出てきたのだ。
そして、怜の、その腕を、世界で一番安全な場所だと、判断してくれたのだ。
怜が、息を殺して、じっと動かずにいると、やがて、彼の体から、ゴロゴロ、ゴロゴロ、という、今まで一度も聞いたことのなかった、穏やかで、小さな寝息が、聞こえてきた。
怜の目から、一筋の、温かい涙が、こぼれ落ちた。
完璧ではない。
傷だらけで、不器用で、どうしようもない、自分と、この猫。
でも、それで、よかったのだ。
二人の間には、静かで、しかし、この世のどんな論理よりも、強く、確かな、信頼の絆が、確かに、生まれていた。
窓から差し込む月明かりが、そんな不完全なパートナーたちを、優しく、照らし出していた。

あとがき
この物語を読み終えたあなたへ
最後まで、この不器用で、傷だらけの魂の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。
私たちは、誰しも、心の中に、怯えた小さな猫を飼っているのかもしれません。
「ちゃんとしなきゃ」という呪いで、自分自身を檻の中に閉じ込めてしまう、弱くて、不完全な自分。
主人公の怜は、自分とそっくりな猫と出会ったことで、初めて、その檻の扉を開けることができました。
この物語が、あなたの心の中にいる、傷ついた猫の存在に気づき、そっと、優しく寄り添ってあげる、ささやかなきっかけになれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。