まえがき
扉を開ける前のあなたへ
愛する者のために、自分があまりにも無力だと感じたことは、 ありませんか。
言葉も、理屈も、何一つ届かない時、 私たちにできるのは、ただ、そばにいて、 その背中を、そっとさすることだけなのかもしれない。
これは、一つの小さく、尊い命の灯火が、 母と娘の、それぞれの無力さと、不器用な愛情を静かに照らし出す物語。
あなたの胸の奥にある、陽だまりのような記憶に、 そっと触れる物語です。
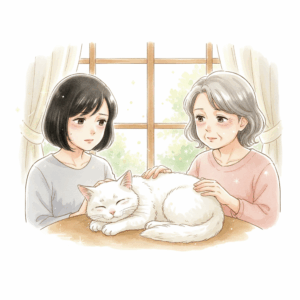
宮内聡美(みやうち さとみ)、三十八歳、製薬会社の研究職。
彼女の世界は、分子式と臨床データ、そして再現可能なエビデンスで構築されていた。
物事の因果関係を、論理的に説明できないことは、好きではなかった。
それは、人間関係においても同じだった。
感情の波や、言葉の裏に隠された意図といった、非科学的なものを読み解くのは、昔から少し苦手だった。
そんな彼女の生活が、一つの、抗うことのできない自然の摂理によって、根底から揺らぎ始めていた。
愛猫のシロ、十八歳。
聡美が、親元を離れて大学に入学した春に、ペットショップで出会った白い日本猫。
彼女の孤独な学生時代も、がむしゃらに働いた二十代も、そして、少しだけ人生に疲れた三十代も、ただ静かに、ずっとそばにいてくれた。
その、かけがえのない相棒が今、緩やかに、しかし確実に、命の終わりに向かって歩んでいた。
「慢性腎臓病です。今後は、ご自宅での皮下点滴が必要になります」
獣医師の冷静な声が、聡美のロジカルな思考を鈍らせた。
彼女の生活は、その日から一変した。
朝、誰よりも早く起き、シロのための療法食をふやかし、数種類の薬を砕いて混ぜ込む。
夜、どんなに疲れて帰宅しても、そこからが本番だった。
アルコール綿の匂い、点滴パックの無機質な感触、そして、針を刺す、あの瞬間。
シロの、骨張った背中の皮膚をつまみ上げ、震える指先で針を刺すたび、聡美の心はすり減っていった。
日に日に痩せていくシロの体、そして、点滴の最中に、か細い声で鳴くその姿を見るたび、「これは、本当にシロのためなのだろうか」という、答えの出ない問いが、彼女の胸を締め付けた。
仕事と介護の両立は、想像を絶するほど過酷だった。
学会の準備で忙殺される日々。
重要な実験の最中も、頭の片隅では「シロは、ちゃんと水を飲んでいるだろうか」という不安が渦巻いている。
聡美は、心身ともに、追い詰められていた。
そんなある日、一本の電話が鳴った。
実家の母親、佳代からだった。
「聡美? あなた、ちゃんと食べてるの? シロちゃんも、大変なんでしょう。お母さん、来週から、そっちに行くから」
「え? いい、大丈夫だから。一人でできる。私、研究職なのよ? こういうのは、マニュアル通りにやれば…」
「いいのよ」母の声が、ほんの少しだけ、寂しそうに揺らいだ。
「お父さんも、最近は釣り仲間と泊まりがけで出かけることばかりだしね。家にいても、やることがないのよ。シロちゃんにご飯作ってあげるくらい、させてちょうだい」
一方的に切られた電話を握りしめ、聡美は深いため息をついた。
母の、こういうお節介で、心配性なところが、昔から少しだけ、重荷だった。
***
招かれざる援軍、宮内佳代(六十五歳)は、一週間後、大きなボストンバッグを抱えて、予告通りに上京してきた。
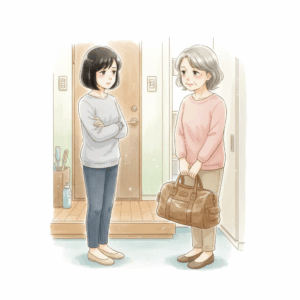
「まあ、狭いけど、片付いてるじゃない」
土足で心の中に踏み込んでくるような母の物言いに、聡美は「ここで暮らしてるんだから、当たり前でしょ」と、棘のある返事をしてしまう。
二人の間には、再会して数分で、いつもの、ぎこちない空気が流れ始めた。
聡美は、母の存在を無視するように、黙々とシロの世話を始めた。
しかし、佳代は、そんな娘の態度を気にも留めず、何も言わずに、キッチンで買ってきた食材を広げ始めた。
やがて、部屋に、聡美が忘れていた、懐かしい煮物の匂いが立ち込める。
「聡美、ご飯よ。食べないと、体、持たないわよ」
出された食事は、ただ、温かかった。
佳代の真価が発揮されたのは、夜の点滴の時間だった。
聡美が、いつものように緊張でこわばる手で準備をしていると、佳代が「ちょっと、貸してごらんなさい」と、こともなげに点滴セットを手に取った。
「シロちゃん、いい子ねえ、ちょっとチクっとするだけよ」
驚いたことに、母の手つきは、実に手際が良かった。
シロの背中を優しく撫で、どこかのツボでも知っているかのように、的確な場所に、す、と針を刺す。聡美がやると、あれほど嫌がって鳴いたシロが、佳代の腕の中では、喉をかすかに鳴らしている。
「…なんで、そんなに上手なの」
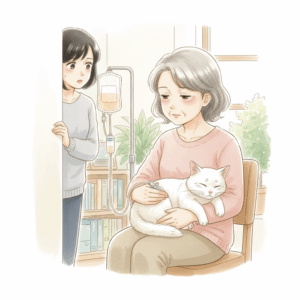
思わず漏れた聡美の問いに、佳代は、シロの背中を撫でながら、こともなげに答えた。
「さあねえ。昔から、手先だけは器用だったから」
その日から、奇妙な三人の共同生活が始まった。
日中、聡美が仕事に行っている間、佳代がシロの世話をする。聡美が帰宅すると、温かい食事が用意されている。
そして、夜の点滴は、いつの間にか佳代の役目になっていた。
言葉を交わす時間は、少ない。
聡美は、母の過干渉から逃れるように、自室にこもりがちだった。
だが、母とシロがリビングで過ごす、その穏やかな気配が、聡美の荒んだ心を、少しずつ、しかし確実に、癒やしていくのを、彼女は感じていた。
ある夜、聡美は、リビングのソファで、うたた寝している母の姿に、ふと足を止めた。
傍らの床には、シロが静かに眠っている。
母の膝から、一枚の古いアルバムが滑り落ちそうになっていた。
そっと拾い上げ、開いてみる。
そこには、七五三の晴れ着を着て、ぎこちなく笑う、幼い自分の姿があった。
隣で、今よりもずっと若い母が、満面の笑みで自分を抱きしめている。
聡美は、そのページを、ただ、静かに見つめていた。
お気に入りのマグカップ、《月光蟲》のロゴが、冷たい部屋の中で、微かに浮かび上がって見えた。
***
その夜、事件は起きた。
佳代が、珍しく「昔の友達と会ってくるわ」と、夕食後に出かけていった。
久しぶりに、聡美とシロの、二人だけの夜だった。
点滴の時間。聡美は、深呼吸して、針を手に取った。
「シロ、いい子だ。すぐに終わるからな」。
しかし、その日に限って、シロがひどく嫌がった。
針を刺した瞬間、今まで見せたこともない力で暴れ、点滴の針が、腕から抜けてしまった。
チューブから、透明な液体が虚しく床にこぼれる。
「シロ! ダメじゃないか!」
思わず、声を荒らげてしまう。
その声に驚いたのか、シロは、怯えたように部屋の隅にうずくまり、か細い声で鳴いた。
その姿を見た瞬間、聡美の中で、張り詰めていた糸が、ぷつりと切れた。
「ごめん…ごめんね、シロ…」
床に崩れ落ち、嗚咽が漏れる。
「私が、シロを苦しめてるだけじゃないの…! こんなの、ただの、私の自己満足じゃないの…!」
生きるということは、素晴らしいことだ。
でも、死に向かう時間を、無理やり引き延ばすことは、本当に、正しいことなのだろうか。
研究者として、命の尊厳を誰よりも考えてきたはずなのに、自分のこととなると、何もわからない。
わからない、わからない、わからない。
パニックに陥った聡美の背中に、その時、そっと、温かい手が触れた。
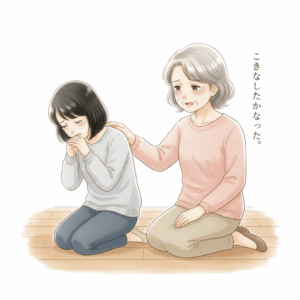
玄関のドアが開く音に、気づかなかった。帰宅した、母だった。
佳代は、何も言わなかった。
ただ、聡美の隣に静かに座り、その震える背中を、ゆっくりと、何度も、何度も、さすり続けた。
やがて、落ち着きを取り戻した聡美の耳に、母の、静かな呟きが届いた。
「…あなたが小さい頃、喘息持ちでね。夜中に、何度も、苦しそうに発作を起こしたのよ」
「……」
「お医者様は、薬をくれて、吸入器をくれて、安心させてくれるけどね。夜中に、ヒューヒューって、苦しそうな寝息を聞いてると、親は、何もできないの。ただ、こうやって、背中をさすることしか、できなかった」
佳代の手が、聡美の背中を、優しく、しかし、確かな重みをもって、さする。
「代わってあげたいのに、代われない。苦しいだろうに、何もしてあげられない。…親なんて、思うてるよりずっと、無力なもんよ。でもね、信じるしかないの。
この子が、明日も、ちゃんと目を覚ましてくれるって」
そして、佳代は、ぽつりと、こう付け加えた。その声は、微かに、震えていた。
「…それはね、聡美。今の、お母さんも、同じなのよ。あなたが、たった一人で、遠い街で、心をすり減らしているんじゃないかって…。心配で、心配で、でも、電話一本かけるのも、迷惑じゃないかって、躊躇って…。何もしてあげられない。お母さんにできることと言ったら、こうやって、得意でもない煮物を作って、あなたの背中をさすることくらいなのよ」
その言葉に、聡美の脳裏に、忘れていた光景が、鮮やかに蘇った。
夜、苦しい咳と共に目を覚ますと、いつも、母がそばにいた。
そして、こうやって、背中をさすりながら、静かな声で、子守唄を歌ってくれていた。
聡美は、その温かい手の感触と、穏やかな歌声に安心して、また眠りにつくのが常だった。
自分は、ずっと、与えられてきたのだ。言葉になどならない、ただ、ひたむきで、不器用で、そして、同じように無力感に苛まれながらも、必死で差し出された、無償の愛を。
その温もりがあったから、自分は、今、ここにいる。
「…お母さん」
「ん?」
「ありがとう」
その一言を言うのに、三十八年もかかってしまった。

***
その夜を境に、母と娘の間に、穏やかな時間が流れるようになった。
数週間後。よく晴れた、春の日の午後だった。
シロは、窓辺の一番暖かい場所で、聡美と佳代に交互に体を撫でられながら、眠るように、静かに息を引き取った。
その寝顔は、不思議なほど、安らかだった。
深い、深い悲しみの中、しかし、聡美の心は、不思議と、満たされていた。
シロが、その命の最後の時間を使って、教えてくれたこと。
それは、当たり前すぎて、見えなくなっていた、家族という名の、不器用で、しかし、どうしようもなく温かい絆だった。
駅のホーム。
出発のベルが鳴り響く。
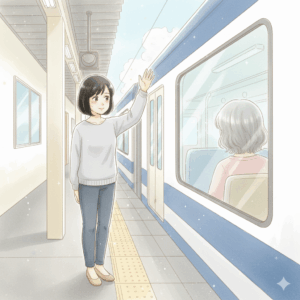
「じゃあ、聡美。体に気をつけるのよ」
「うん。お母さんも」
当たり障りのない言葉を交わし、佳代は、ゆっくりと列車に乗り込んだ。
ドアが閉まり、ゆっくりと、列車が動き出す。
窓の向こうで、母が、少しだけ、泣き笑いのような顔で、手を振っている。
その背中は、昔、聡美の記憶の中にあった、大きく、頼もしかった背中よりも、いつの間にか、少しだけ、小さくなっているように見えた。
聡美は、その小さな背中が見えなくなるまで、ただ、涙で滲む景色の中、静かに、手を振り続けた。
あとがき
この物語を読み終えたあなたへ
最後まで、この陽だまりと背中の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。
私たちが受け取ってきた愛情は、もしかしたら、完璧に美しく、 selfless なものばかりではなかったのかもしれません。
その裏側には、与える側の、どうしようもない孤独や、不器用な祈りが、そっと隠されていたのかもしれない。
主人公の聡美は、母の告白を通して、初めてその事実に気づきます。
シロが命の最後に繋いだ、二つの手のひらの温もり。
この物語が、あなたの心の中にある、誰かの不器用な手のひらの温もりを、思い出すきっかけになれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。