まえがき
扉を開ける前のあなたへ
幸せになるための分析を、繰り返すほど、 心の声が、ただのノイズに聞こえてくる。
そんな夜は、ありませんか。
頭で導き出した「正解」に、心がついていかない。
一番大切なはずのサインを、私たちは、あまりにも簡単に見過ごしてしまうのかもしれません。
これは、完璧な分析も、絶対の神託も、すべて捨てて、 不器用な優しさを映し出す、正直な「鏡」を覗き込む、 そんな、あなたのための物語です。

相沢育美(あいざわ いくみ)、三十六歳、化粧品会社のマーケター。
彼女のデスクの上には、最新の市場データと消費者インサイトが完璧に整理されている。
円グラフ、ヒートマップ、散布図。あらゆる事象を分析し、数値化し、最適解を導き出すのが彼女の仕事であり、得意分野だった。
しかし、その優れた分析能力は、ひとたび「恋愛」という名の市場に足を踏み入れると、途端にポンコツのナビゲーションシステムと化す。
「年収800万以上、身長175cm以上、四大卒、長男以外、そして…清潔感」
育美は、お気に入りのブックカフェ《月光蟲》のロゴが入ったマグカップを片手に、タブレットに表示された婚活アプリのプロフィールを、まるで競合他社のデータを分析するかのように睨みつけていた。
三十五歳を過ぎてからというもの、彼女の恋愛は常に減点法だ。
ときめきや直感といった、ROI(投資収益率)の計測が不可能なファクターは、限りなく後回しにされる。
だが、その分析の結果選んだ「優良物件」に限って、致命的なバグが見つかるのだ。
そんな彼女の日常における、唯一の非論理的で、しかし絶対的な存在が、愛猫の小豆(あずき)だった。
艶やかな黒い毛並みを持つ、年齢不詳の元保護猫。
その琥珀色の瞳は、時折、すべてを見通しているかのような、古代の叡智を宿しているように見えた。
その小豆が、育美の婚活に大いなる転機をもたらしたのは、ある秋の日の午後だった。
育美は、アプリで出会った「完璧」な男性、工藤という名のコンサルタントを、初めて自宅に招いた。
年収、学歴、ルックス、会話のスマートさ。
育美の分析シートの項目は、すべて満点を叩き出していた。
育美が緊張しながらコーヒーを淹れていると、リビングから工藤の穏やかな笑い声が聞こえた。
何事かと顔を出すと、そこには、彼女の分析能力を試すかのような、実に微妙な光景が広がっていた。
あの小豆が、工藤の足元に出てきている。
しかし、その距離は三メートルほどあり、決して近づこうとはしない。喉は鳴らさず、ただ、琥珀色の瞳で、じっと彼の本質を見定めるかのように、値踏みするような鋭い視線を送っているのだ。
その時、工藤は実にスマートな手つきで懐から、小さな銀色のパウチを取り出した。
「猫を飼っている友人から、お近づきの印にって言われてね」。

最高級の猫用おやつ。
その抗いがたい匂いに、小豆の鋭い視線は、いとも簡単に揺らいだ。
おやつを夢中で食べ終えた小豆は、満足げに顔を洗い、彼の膝の上でうっとりと喉を鳴らし始めた。
育美は、小豆の最初の、あの僅かな警戒心を「初期データのノイズ」だと判断した。
完璧なスペックと、スマートな手土産。そして、「結果的に喉を鳴らした」という、最終的なアウトプット。
彼女の分析シートは、やはり満点を叩き出していた。
その完璧なロジックが崩壊したのは、一週間後。
同僚のSNSで、彼が妻子持ちであることを知った時だった。
家に帰り、小豆の黒い毛並みに顔をうずめながら、育美の中で、バラバラだったピースが、一つの戦慄すべき結論へと組み上がっていった。
私のスペック分析が間違っていただけじゃない。
小豆は、最初、気づいていたんだ。
彼の胡散臭さに。
あの距離、あの値踏みするような視線。
それこそが、最も重要な「初期データ」だったんだ。
それなのに、私は、おやつという名の賄賂と、完璧なスペックというノイズに目がくらみ、猫が発した、
最も純粋な直感を見過ごした。
私のロジックが、猫の直感を上書きして、失敗したんだ!
この日を境に、育美の婚活は、新たなフェーズへと移行した。
彼女はそれを、密かに「猫様による最終面接」と名付けた。
小豆の「初期反応」こそが、唯一信頼できる神託なのだ、と。
***
「猫様面接」は、育美をより深い迷宮へと誘った。
IT企業の営業マンは、小豆に駆け寄り威嚇され、即お見送り。
その夜、育美は会社で吉野湊(よしの みなと)が、皆が帰った後、一人でシュレッダーのゴミを片付けている姿を見て、胸に小さな温かいものが灯るのを感じた。
「ああいうのが、本当は…」。
次に現れた物静かな公務員は、小豆を完全に無視し、小豆からも無視され、お見送り。
その翌日、育美は給湯室で、吉野が会社の枯れかけた観葉植物に、こっそり水と栄養剤を与えているのを目撃した。
誰に褒められるわけでもない、その小さな優しさに、育美の心は大きく揺れた。
そして、三人目の挑戦者が現れる。
大手建築事務所に勤める、斎藤。
スペックは完璧、清潔感があり、会話も知的で面白い。
そして彼は、猫の扱いが、神がかり的に上手かった。
彼は無理に近づかず、ただ静かにソファに座り、本を読んでいた。
すると、三十分後、小豆の方から彼に近づき、足元にスリスリと体をこすりつけ、喉を鳴らし始めたのだ。
初期反応、完璧。
育美のルールによれば、彼は「合格」だった。
しかし、育美は、どうしても彼を好きになれなかった。
二度目のデートで、お洒落なレストランで完璧なエスコートをされながら、彼女の心は、空っぽだった。
データは満点。
猫の神託も下った。
なのに、なぜ。
どうして私の心は、会社のデスクで不器用にお茶を淹れる、吉野の姿ばかりを思い出してしまうのだろう。

「ごめんなさい」。
育美は、初めて、猫の神託を破った。
完璧な男に、自ら別れを告げたのだ。
自分の心が、「NO」と叫んでいることに、もう気づかないふりはできなかった。
自分のルールに、がんじがらめになっている。
吉野への想いが募るほど、そのルールが、巨大な壁となって立ちはだかる。
「犬派」の彼を、小豆が受け入れるはずがない。
もし、彼が威嚇されたら? 無視されたら?
私は、自分のこの気持ちを、諦めなければならないのだろうか。
悩んだ末、育美は一つの結論を出した。
この曖昧な気持ちに決着をつけるためにも、彼を「最終面接」にかけるしかない。
これが、最後だ。
「吉野くん、今度、うちに来ない?お礼に、ご飯ごちそうするから」
震える声で誘うと、吉野は一瞬驚いたように目を見開き、そして、はにかむように「…はい、喜んで」と頷いた。

***
運命の日。
育美の心臓は、まるで暴風雨の中の小舟のように、激しく揺れていた。
吉野は、「お邪魔します」と、少し緊張した面持ちで部屋に入ってきた。
育美は、彼をリビングに通すと、深呼吸した。
ソファの隅では、小豆が琥珀色の瞳を爛々と輝かせ、侵入者をじっと見据えている。
さあ、神託の時だ。
「…あ、猫、いるんだね」
吉野が、小豆の存在に気づいた。
彼は、ただソファの前に立ったまま、穏やかな表情で小豆を見つめ返し、そして、育美の方を振り返って、静かに微笑んだ。
「君の猫、綺麗だね。毛並みが、ビロードみたいだ」
その言葉には、下心も遠慮もなかった。
ただ、目の前にいる美しい生き物に対する、純粋な敬意だけが込められていた。
育美の胸が、温かくなる。
だが、その時だった。
吉野が、犬派であるが故の不器用さで、ほんの少しだけ、小豆が警戒する距離に、無意識に、しかし確実につま先を半歩、踏み入れてしまったのだ。
その瞬間、小豆の体が、ぴん、と緊張に満ちた一本の線になった。
喉の奥から、かすかに「ぅ…」という唸り声が漏れる。
琥珀色の瞳が、鋭く細められた。
育美の頭の中で、警報が鳴り響いた。
(システムアラート:警戒レベル1。ルールによれば、これは減点対象。面接は中止すべきだ)
(違う!)
もう一人の自分が、叫んだ。
(彼は悪気がない。ただ、知らないだけだ。犬と猫の距離感が、違うだけだ!)
思考が、激しく衝突する。ルールに従うのか。自分の心を、信じるのか。
そして、育美は、初めて、自分の意志で、神託を待つことをやめた。
彼女は、吉野と小豆の間に、そっと滑るように割って入った。
吉野を責めるのでも、小豆を叱るのでもなく、ただ、ごく自然に。
「ごめんね、吉野くん。この子、すごく人見知りで…。ここから見るのが、一番綺麗に見える特等席なの」
そう言って、育美は悪戯っぽく微笑んだ。
彼女が、自らの判断で、吉野を小豆から守り、そして、小豆を吉野から守った。
猫の神託を待つのではなく、自らの判断で、二人の関係性を、彼女がコントロールしたのだ。
その小さな、しかし偉大な一歩を踏み出した瞬間、育美の中で、何かが音を立てて繋がった。
ああ、そうか。
小豆は、「神託」を下していたわけじゃない。
彼女は、ただの「鏡」だったのだ。
相手が、自分より小さく、言葉も通じない、か弱い存在に対して、どう振る舞うのか。
その人間の本質を、ただ静かに映し出していただけだったんだ。
今まで、自分はなんて愚かだったんだろう。
猫の反応という、外部のデータにばかり頼って、自分の目で、自分の心で、相手を見ようとしてこなかった。
大切なのは、猫に好かれるかどうかじゃない。
私が、私の目で見た、この人を信じられるかどうかだ。
育美の目から、一筋の涙がこぼれた。
それは、自分を取り戻した、安堵の涙だった。
「…ありがとう。あの子、小豆っていうの」
育美が微笑むと、吉野は「いい名前だね」と、心から優しく言った。
後日。
会社の帰りに、吉野が少し照れくさそうに、育美に小さな紙袋を差し出した。
「これ…この間の猫ちゃんに。俺、別に猫アレルギーとかじゃないから。少しずつ、仲良くなれたらいいな、って」
袋の中には、猫用のかつお節のおやつが入っていた。
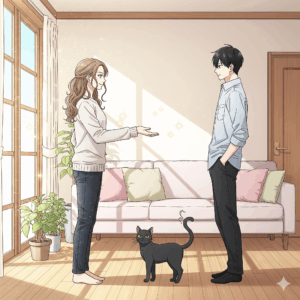
その週末、再び育美の部屋を訪れた吉野。
彼が、おずおずと差し出したかつお節を、小豆は最初、遠巻きに眺めていた。
だが、吉野が焦らず、騒がず、ただ静かに待っていると、やがて、彼女はゆっくりと彼に近づいた。
そして、カリカリと美味しそうにおやつを食べ終えると、初めて、彼の足元に、そっと、そのビロードのような体を一度だけ、こすりつけた。
それは、神託でも、ジャッジでもない。
ただ、一匹の猫が、一人の誠実な人間に、心を開いた、始まりの合図だった。
育美は、そんな二人を、心の底から愛おしいと思いながら、見つめていた。

あとがき
この物語を読み終えたあなたへ
最後まで、この不器用で、愛おしい恋の物語にお付き合いいただき、ありがとうございます。
自分を縛っていたルールを、自らの手で破る。
それは、とても怖くて、でも、何よりも自由な一歩なのだと思います。
主人公の育美は、神託を待つことをやめ、自分の意志で行動したことで、初めて、目の前にいる人の本当の姿と、自分自身の本当の気持ちに向き合うことができました。
あなたの日常にも、もしかしたら「こうあるべきだ」という、見えないルールがあるかもしれません。
でも、あなたのそばにいる猫や、心惹かれる誰かは、そんなルールとは関係なく、ただ、今のあなたの心を映し出す、静かで、正直な鏡なのかもしれません。
この物語が、あなたがあなた自身の心のコンパスを信じて、小さな、しかし最も偉大な一歩を踏み出す、ささやかな勇気となれたなら、作家として、これ以上の喜びはありません。